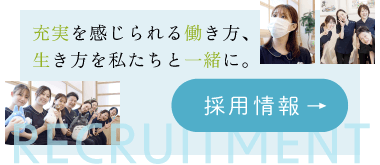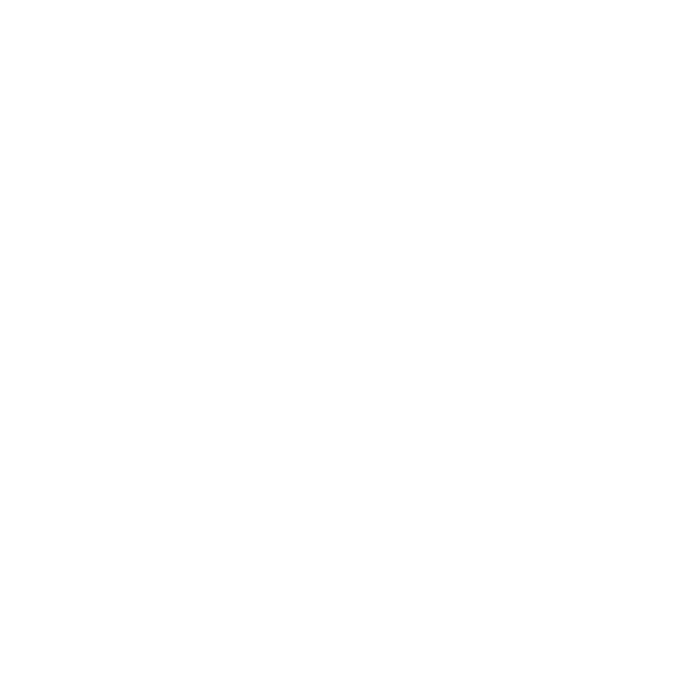「緊張したりストレスを感じるとすぐにお腹が痛くなる」「おならが頻繁に出て、しかも臭いが気になる」「便秘が続いたり、スッキリしない感じがいつもある」
こんな悩みを抱えている方はいませんか?消化器系の検査で異常が見つからないのに、お腹の不調が続く場合、それは「過敏性腸症候群(IBS)」の一つの病型とされる「ガス型」なのかもしれません。今回は、ガス型の過敏性腸症候群の症状や考えられる原因、そして改善方法について詳しく解説します。快適に過ごせるよう、ぜひ参考にしてください。
目に見える異常がない病気、過敏性腸症候群とは
日本では、全人口の約10〜20%の人が過敏性腸症候群を抱えていると推定され、若い女性や働き盛りの男性に多く見られるとされています。しかし、日常的な腹痛や下痢などの症状を病気とは考えず、医療機関を受診しない人も多いことから、潜在的な患者数はさらに多い可能性があります。
過敏性腸症候群は命に関わるものではありません。ただし、症状が日常生活に支障をきたす場合は適切な対策や治療が必要です。
検査では異常がない
この病気の特徴は、検査を行っても腸に潰瘍や炎症といった目に見える異常が確認されないことです。
- お腹が痛い
- ガスがたまってお腹が張る
- 下痢が続く
こういった症状は一般的に経験するものですが、病院で検査をしても特に異常が見つからない場合があります。そんな場合、「原因は何だろう」と悩むことも少なくありません。
体の不調の中には、検査で異常が確認できるものと、そうでないものがあります。検査で原因が明確になる病気は「器質的疾患」と呼ばれますが、検査で異常が見つからない場合には「機能的疾患」と分類されます。腸における代表的な機能的疾患が「過敏性腸症候群」です。
いろいろなタイプがある
過敏性腸症候群は、腸そのものに目に見える異常がないにもかかわらず、腸が正常に機能しないことで、さまざまな不調を引き起こします。この病気にはいくつかのタイプがあり、下痢が主な症状の「下痢型」、便秘が続く「便秘型」、さらに下痢と便秘を繰り返す「混合型」、お腹の張りやガスの症状が主な特徴の「ガス型」があります。それぞれ症状が異なるため、同じ病気でも人によって感じ方が違うことが特徴です。
ガスでおなかが張る症状の過敏性腸症候群「ガス型」
過敏性腸症候群の「ガス型」は、お腹が張る、頻繁におならやゲップが出るといった症状が特徴とされています。おならを我慢しなければならない場面が多くなるため、人前では特に辛い思いをします。頻繁にトイレに行ったり、ガスを出すために工夫をしても、臭いや音が気になるため、精神的にも大きな負担となります。
過敏性腸症候群「ガス型」の原因
ガス型の原因としては、空気の飲み込み、食事内容、ストレスによる腸のセロトニン分泌の乱れ、などが挙げられます。
空気の飲み込み
腸にガスがたまる原因の多くは、空気を飲み込むことによると言われています。人は唾液を飲み込む際に少量の空気も一緒に飲み込みますが、ストレスや緊張で唾液を飲み込む回数が増えると、「空気えん下症」または「呑気症」と呼ばれる状態が起こります。
空気を飲み込む行動は、汁物・麺類をすする、炭酸飲料、ガムを噛む、早食いをする、飲み物をストローで飲むなど、普段の何気ない行動の中で起こります。
飲み込まれた空気の一部は人によってはゲップとして排出されますが、残った空気は腸に流れ込みます。この腸にたまった空気が、ガスの原因となります。過敏性腸症候群は、腸が敏感であるため、通常の量のガスでも不快感や痛みを引き起こす場合があります。
高FODMAP食
過敏性腸症候群のガス型の原因には、「高FODMAP食」の摂取も大きく関与していると考えられています。FODMAPとは、発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、糖アルコールの略で、これらの糖質は小腸で吸収されにくく、大腸で発酵しやすい性質を持っています。その結果、お腹にガスが溜まりやすく、ガス型の症状を引き起こす可能性があるのです。
具体的な高FODMAP食品には、パンやパスタなどの小麦製品、タマネギやアスパラガスなどの野菜、豆類、牛乳やヨーグルトといった乳製品などが挙げられます。これらを過剰に摂取すると、腸内でガスが大量に発生し、腹部の不快感や膨満感、さらにはおならの増加といった症状を悪化させる可能性があります。
治療としては、まず高FODMAP食を避けることで症状が改善するかを確認し、その後少しずつ高FODMAP食品を再導入して、特定の食品が症状に影響しているかをチェックする方法があります。
セロトニンの関与
空気の飲み込みだけが「ガス型」の原因ではありません。過敏性腸症候群には、セロトニンという神経伝達物質が深く関与しています。強いストレスや不安があると、腸でのセロトニン分泌が増加し、腸の運動が乱れることで症状が現れるのです。
腸の動きが過剰になると内容物が早く流れすぎて下痢になり、逆に動きが低下すると便が腸内に長く留まり、水分が吸収されることで硬いコロコロとした便になります。また、腸の一部の動きが低下すると、その場所にガスや内容物がたまり、腹部膨満感や腹痛を引き起こします。
過敏性腸症候群「ガス型」の症状
「ガス型」は、お腹が張る、頻繁におならやゲップが出るといった症状が特徴です。命に関わる病気ではありませんが、症状が仕事や学校生活に支障をきたすことがあります。ストレスが原因で悪化しやすいため、重要な会議や試験の際など、緊張や不安が強まる場面で症状が顕著になることがあります。
過敏性腸症候群「ガス型」への対処方法
- ストレス対策
- 空気の飲み込み対策
- うまくガスを出す
- 薬物療法
これらの対策を組み合わせることで、過敏性腸症候群「ガス型」の症状を軽減できます。自分の生活に取り入れやすい方法から試してみてください。
ストレス対策
ストレスはこの症状の大きな原因の一つとされています。生活リズムが乱れていないかを見直し、十分な休息をとりましょう。ストレス源(仕事や人間関係など)がある場合、解決に向けた取り組みやストレスを和らげる方法を探ることが大切です。気分が落ち込み、日常生活に支障をきたすようであれば、心療内科(メンタルクリニック)などでのカウンセリングや治療も検討しましょう。
空気の飲み込み対策
緊張やストレスで無意識に空気を飲み込むのを防ぐため、食事は早食いを避け、ゆっくり噛んで少量ずつ食べることを心がけてください。また、炭酸飲料やガムは控え、汁物や麺類を食べる際も飲み込む量を減らすよう意識しましょう。ストレスが原因で空気嚥下が増えることもあるため、リラックスした環境で食事をとることが重要です。
うまくガスを出す
毎朝、家を出る前に便やガスをしっかり排出する習慣をつけてみましょう。そのためには早寝早起きや朝食の習慣が役立ちます。食後は余裕を持ち、トイレに座る時間を確保してください。我慢し続けることは腸への負担を増やします。日中にガスがたまりそうになったら、無理に我慢せずトイレで解消することが大切です。
薬物療法
セルフコントロールが難しい場合には、医療機関で内服薬を処方してもらいましょう。ただし、ガスによる腹部膨満感を改善できるような薬剤はあまりないというのが実情です。医師と相談しながら症状に合った薬を見つけること、食事などの指導を仰ぐことができます。焦らず、少しずつ症状を改善していきましょう。
過敏性腸症候群「ガス型」で控えた方がよい食べ物
過敏性腸症候群の方は、「ガスがひどくたまる」と感じることが多いです。ただし、様々な研究結果によると、実際に他の人より多くのガスを発生させているわけではないようです。過敏性腸症候群の方には、ガスが腸にたまりやすいという特性があります。腸の神経や筋肉の働きに問題があることが関係していると考えられ、腸が過度に敏感になっている場合、通常の量のガスでも痛みや不快感を引き起こすことがあります。
- 高FODMAP食品
- 脂質の多い食品
- カフェイン・アルコール
- 乳製品
- 香辛料
他の人にガスを引き起こす食品が、自分には影響しないかもしれません。また、自分に効果があると感じた対策が、他の人には全く効果がない場合もあります。どの食品が症状を悪化させるのか、自分の体に合った方法を見つけるためには試行錯誤が必要です。日記をつけて食事内容や症状を記録し、何が自分に合うのかを把握することが対策の第一歩になります。
高FODMAP食品
高FODMAP食品とは、腸で発酵しやすく吸収されにくい糖類を多く含む食品です。これらは腸内でガスを発生させる原因となるため、避けた方がよいとされています。大麦、小麦、玉ねぎ、豆類、乳製品(乳糖を含むもの)などが該当します。これらの食品を摂取すると、ガス型の症状が悪化しやすいため注意しましょう。
関連記事:低FODMAP(フォドマップ)食の効果とは?お腹の不調を改善する食事法
脂質の多い食品
脂肪分の多い食品は、腸内で脂肪酸を生成し腸を刺激します。これがガスや下痢の原因となることがあります。揚げ物やベーコン、ソーセージといった加工肉類は、特に注意が必要です。これらは腸に負担をかける食品とされています。
カフェイン・アルコール
カフェインやアルコールは、腸の動きを刺激して症状を悪化させる可能性があります。コーヒーやエナジードリンク、お酒などを頻繁に飲む人は発症リスクが高まるため注意しましょう。また、利尿作用があるため体内の水分が不足し、腸内の悪玉菌が増える要因にもなり得ます。
乳製品
乳製品は、乳糖不耐症の人に特に問題を引き起こします。牛乳やヨーグルト、アイスクリームなどは腸内環境を悪化させる可能性があります。乳製品の中には高FODMAP食品も多く含まれるため、摂取量や頻度に注意しましょう。
香辛料
香辛料やスパイスを多く含む食品は、腸の動きを過剰に活発化させることがあります。特に唐辛子に含まれるカプサイシンは、腸を刺激してガス、下痢、腹痛を引き起こす可能性があります。カレーやピリ辛の料理は控えましょう。
過敏性腸症候群のガス型以外の種類
過敏性腸症候群はタイプごとに症状や対策が異なります。
下痢が主な症状の「下痢型」
下痢型では、軽い緊張や不安を感じただけで、突然激しい下痢に見舞われるのが特徴です。たとえば、通勤中に電車を降りてトイレに駆け込むといった状況がよく見られるケースです。
このタイプは「神経性下痢」とも呼ばれ、以前は仕事や私生活でストレスを抱える男性に多いとされていました。現在では、仕事やストレスを抱える女性にも多く見られます。
また、ストレスだけでなく、下痢を引き起こしやすい食品や食べ方も影響することがあります。水のような便や粘度の高い便が頻繁に出る場合は、このタイプを疑いましょう。
便秘が続く「便秘型」
便秘型は、慢性的な便秘やコロコロとした小さい便が主な症状です。このタイプは女性に多くみられ、便秘だけでなく腹部の不快感や腹痛を伴うことも少なくありません。
ストレスが腸の収縮運動を低下させることで便秘が悪化すると考えられています。さらに、食物繊維の不足も便秘型を悪化させる要因です。水溶性食物繊維を取り入れることや、ストレスを軽減することで改善が期待できます。
下痢と便秘を繰り返す「混合型」
混合型では、下痢と便秘が交互に現れます。このタイプは「交代制便通異常」とも呼ばれ、数日おきに下痢と便秘を繰り返すのが特徴です。
腹痛や腹部の不快感が伴い、便が完全に出きらない感覚を持つこともあります。便の硬さが日によって変わり、柔らかくなったり硬くなったりするのもこのタイプの特徴です。ストレスや生活習慣の影響が大きいため、症状のパターンに応じた対応が必要になります。
過敏性腸症候群になりやすい方
過敏性腸症候群になりやすい方には、いくつかの特徴が見られます。これらの要因が複雑に絡み合うことで、症状が引き起こされると考えられています。
ストレスを感じやすい性格
真面目で責任感が強く、仕事に熱心な人は、他人からの評価を気にする傾向があります。このような性格の方は、ストレスを感じやすく、その影響が腸に現れやすいと言われています。
生活習慣が乱れている
十分な睡眠が取れていない、食事が不規則で栄養バランスが偏っている、など、生活リズムが乱れている方もリスクが高まります。腸の健康は生活習慣と密接に関係しているため、不規則な生活が症状の引き金になることがあります。
几帳面な性格
几帳面で細やかな性格の人は、細かいことを気にしやすく、プレッシャーや緊張を感じやすい傾向があります。このような性格も過敏性腸症候群を引き起こす一因とされています。
心の健康状態が悪い
心の状態が不安定だったり、心配事が多い場合、腸の働きが影響を受けやすくなります。特に気分が落ち込みやすい状態や不安感が強いと、腸に症状が現れることが多いです。
過敏性腸症候群の原因と対策
- ストレス
- 暴飲暴食
- 不規則な生活
腸の動きを調整する自律神経の異常や、消化管が過敏になり痛みを感じやすくなる状態、さらには精神的な不安やストレスといった心理的要因が関係します。これらの要因が複雑に絡み合い、症状を引き起こしたり悪化させたりします。神経質な性格の方が発症しやすい傾向があり、暴飲暴食やアルコールの過剰摂取、過度な肉体的・精神的疲労がトリガーとなることもあります。
食生活に注意する
食生活の見直しが腸の調子を整える第一歩です。食物繊維を含むバランスの良い食事を、毎日3回規則正しく摂るよう心がけましょう。規則正しい食事はストレスに対抗する力を高め、腸の健康維持にも役立ちます。暴飲暴食は過敏性腸症候群の原因にもなるため、食べすぎには注意が必要です。脂っこい食べ物や香辛料を控え、緑黄色野菜を積極的に取り入れると良いでしょう。
生活リズムを整える
過労や睡眠不足は悪化させる要因となるため、十分な休息を取ることを心がけましょう。さらに、適度な運動を日常生活に取り入れることも効果的です。趣味やリフレッシュできる時間を確保し、心身をリラックスさせることも腸の健康に良い影響を与えます。
運動を取り入れる
ストレッチやウォーキング、散歩など、体に負担をかけない軽い運動が効果的です。朝に散歩をすることで体内時計がリセットされ、腸の働きが整いやすくなるため、特におすすめの習慣といえます。
日常的に座りがちな生活をしている場合でも、週に1時間から始めることで効果が期待できます。無理をせず、日々の生活の中に軽い運動を取り入れてみましょう。継続することで、腸の健康だけでなく、ストレスの軽減や心身のリフレッシュにもつながります。
過敏性腸症候群の検査と診断
過敏性腸症候群の可能性を判断するとともに、がんや炎症性腸疾患などの器質的な異常を排除します。
問診
診察では、患者の自覚症状や生活習慣、日常生活での困りごと、過去にかかった病気(既往症)、家族の病歴(家族歴)、全身状態などを確認します。これにより、症状の原因や日常生活に与える影響を把握し、診断の基礎とします。
バリウム検査
肛門からバリウムと空気を注入し、大腸の形状や粘膜の状態を調べる検査で。X線を使って腸内の炎症や腫瘍の有無を確認します。大腸カメラ検査の代替や補助として行われることがありますが、最近は大腸カメラ検査が楽に受けられるようになってきたこともあり、行われる頻度が減少しています。
大腸カメラ検査(内視鏡検査)
- 血便や発熱、体重減少といったアラームサインがある場合
- 50歳以上
- 大腸疾患の既往歴や家族歴がある方
これらに当てはまる場合は実施されることがあります。この検査では、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内部を詳細に観察します。ポリープやがんなどの異常が見つかった場合は、その場で切除や細胞採取を行うことも可能です。
一人で悩まず、病院を受診しましょう
過敏性腸症候群は、現代のストレス社会とともに少しずつ増えている病気です。特に20〜40代の働き盛りの人に多くみられ、誰にでも発症する可能性があります。この病気は、慢性的な腹痛や下痢、またはお腹の張りといった症状が特徴です。
こうした症状が現れたら、まずご自身の生活習慣やストレスの原因を見直してみましょう。規則正しい生活や食事、適度な運動を心がけるとともに、ストレスを軽減する方法を取り入れてみてください。それでも症状が改善しない場合は、近くの消化器科を受診して、専門的な診察と治療を受けることをおすすめします。早めの対処が、症状の悪化を防ぐ鍵となります。