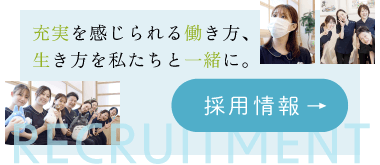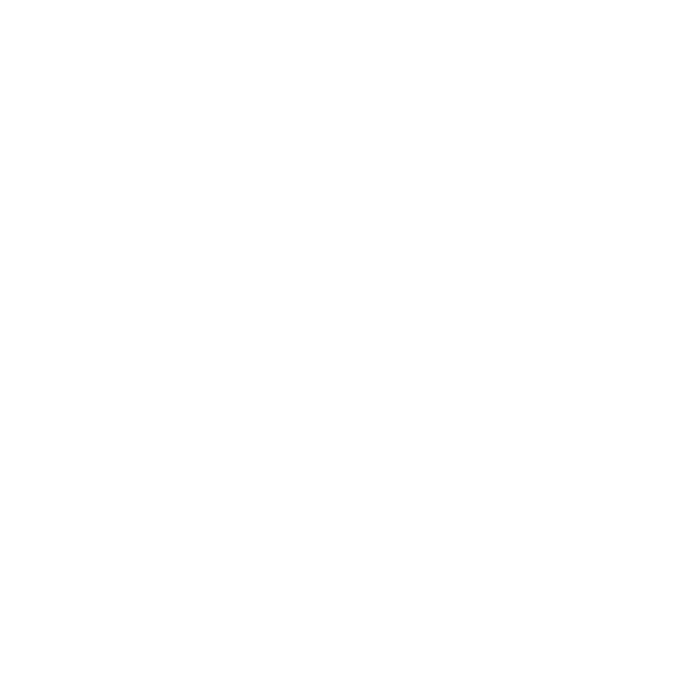刺身やしめさばを食べた後、数時間して突然胃が激しく痛み、吐き気や嘔吐が起こることがあります。こうした症状が現れた場合、その原因は「アニサキス」という寄生虫による食中毒かもしれません。魚介類に潜む小さな虫が体内に入り込み、胃や腸で悪さをすることで、こうした不快な症状を引き起こすことがあります。今回はアニサキスによる食中毒の原因と予防法、治療について紹介します。

お寿司を食べた翌日に突然の胃痛、その正体は?
アニサキスとは
アニサキスは寄生虫の一種で、その幼虫は長さ2〜3cm、幅0.5〜1mmほどの白っぽい太めの糸のような見た目をしています。この幼虫は、さまざまな魚介類に寄生していることがあります。
原因となる食品
サバやサンマ、カツオの刺身や寿司、シメサバが原因となるケースが多いとされますが、サケ、アジ、スルメイカ、イワシ、タラ、マス、ニシンなども原因となる可能性があります。また、ホッケ、サワラ・サゴシ、キンメダイ、メジマグロ、アイナメにも寄生していることがあります。
感染経路
アニサキスの幼虫が寄生する魚介類を生で食べたり、不十分な冷凍や加熱処理をした状態で摂取すると、アニサキスの幼虫が胃壁や腸壁に入り込み、食中毒(胃アニサキス症や腸アニサキス症)を引き起こします。このアニサキス症は、海産魚介類の生食が原因となる寄生虫症の中で、日本で最も多く発生しているものです。日本人の生魚を食べる文化と密接に関係している食中毒といえるでしょう。
アニサキスによる病気の種類と症状
アニサキスがいても全く症状が出ない方もいます。同じものを食べても、誰もが発症するわけではないのです。
胃アニサキス症
胃アニサキス症は、アニサキスが体内に入り、胃の壁に噛みつくことで起こる病気です。アニサキスは胃の壁に入り込もうとするのですが、近年の研究では、痛みなどの症状はその行動自体が原因ではなく、体がアニサキスに反応して起こすアレルギー反応です。そのため、症状の現れ方は個人の体質や免疫の状態によって幅広い形で現れることがあります。
症状が激しく出る場合は「急性型」と呼ばれ、魚介類を食べてから数時間から10時間以上後に、強い胃の痛みや吐き気、嘔吐といった症状が現れます。この症状は波のように強まったり弱まったりを繰り返すことが特徴です。
一方で、症状がほとんどない「慢性型」もあり、この場合は自覚症状がなく、胃カメラの検査中に偶然見つかることがあります。
腸アニサキス症
アニサキスが小腸に入り込むと、「腸アニサキス症」という病気を引き起こすことがあります。この場合、魚介類を食べてから半日から数日後に症状が現れるため、原因がアニサキスだと気づかないことも珍しくありません。
主な症状は、強い腹痛や吐き気、嘔吐などです。小腸の深い部分で問題が起こるため、内視鏡で直接治療することが難しい場合があり、治療は痛みや不快感を和らげる対症療法が中心になります。
しかし、症状が進行するとごく希ではありますが腸が詰まる「腸閉塞」や、腸が破れる「腸穿孔」による腹膜炎といった重い状態に至ることがあるという報告もあります。この場合は緊急手術が必要になることもありますので、魚介類を食べた後に激しい腹痛が続く場合は、できるだけ早く病院を受診することが大切です。
消化管外アニサキス症
非常に稀なケースで、アニサキスの幼虫が消化管の壁を突き破り、腹腔内やその周辺の臓器に入り込むことで症状が起こります。この場合、どの部位に影響を及ぼすかによって症状が異なります。
アニサキスアレルギー
アニサキスに対するアレルギー反応によって引き起こされる症状です。通常、アニサキスが体内で生きている間は激しい症状が続きますが、虫が死ぬと症状は徐々に治まります。しかし、アレルギー体質の方の場合、アニサキスが寄生していた魚介類を加熱して食べたとしてもアレルギー症状が出ることがあります。アニサキス自体が抗原となるため、加熱処理などは関係ありません。
症状は、主に蕁麻疹です。ただし、まれにアナフィラキシーショックを引き起こすこともあります。青魚を食べたときに蕁麻疹が出る人は、アニサキスアレルギーが原因かもしれません。
アニサキスによる感染を防ぐための予防方法
- 新鮮なものを選ぶ
- 目視で確認
- 加熱・冷凍を行う
アニサキスは主に魚やイカの内臓部分に寄生しています。しかし、魚の鮮度が落ちると、内臓から筋肉部分へと移動するため、筋肉に移動したアニサキスが原因で食中毒が発生するケースがほとんどです。
魚を購入するときは、新鮮なものを選びましょう。丸ごと1匹で購入した場合は、内臓を速やかに取り除いてください。
調理をする際のポイント
- 60度で1分以上加熱
- マイナス20度以下で24時間以上冷凍
アニサキスによる食中毒を防ぐには、加熱や冷凍で虫を死滅させるか、目視で取り除く方法があります。アニサキスは熱に弱く、60度で1分以上加熱するか、マイナス20度以下で24時間以上冷凍することで死滅します。
刺身などを生で食べる際には、筋肉の中にいるアニサキスを目視で確認し、取り除くことが大切です。特に内臓に近い腹側の筋肉をよく確認すると、発見しやすいとされています。
食べる際のポイント
アニサキスは、調理をする人だけでなく、食べる人も注意を払うことで発見することが可能です。魚を生で食べる際には、目視で確認し、アニサキス幼虫を取り除くよう心がけてください。内臓を生で食べるのは避けましょう。
間違った情報に注意!
一般的な食酢や塩漬け、醤油、わさびではアニサキスを死滅させられません。これらの方法に頼らないよう注意してください。
また、「噛めば大丈夫」とは限りません。アニサキス幼虫は小さく、魚のどこに潜んでいるか分からないため、目で確認しにくいことがあります。さらに、幼虫の表面はなめらかで丈夫であり、細い糸のような形状をしているため、噛み切るのは非常に難しいといえるでしょう。安全のためには、しっかりとした処理が必要です。
アニサキス症の検査
検査は、主に発生箇所に応じて行われます。ほとんどの場合は胃で起こるため、胃カメラが有効な検査方法です。アニサキス症を引き起こす第3期幼生は比較的大きいため、胃カメラを使用すれば容易に確認できます。
アニサキスが小腸や腸管外に移動してしまった場合に行われる検査は、腹部エコーやCT検査です。また、稀にある大腸まで到達するケースでは、大腸カメラによる検査を行うことがあります。
アニサキス症の治療法
アニサキス症の治療は、発症部位によって異なります
胃アニサキス症
胃カメラ検査でアニサキスを確認し、内視鏡に付属する鉗子で摘出します。アニサキスは胃壁にしっかりと食いついており、周囲の粘膜が腫れ上がっていることもありますが、鉗子でつかむことで安全に除去が可能です。除去したアニサキスは内視鏡を通じて体外に取り出します。
すぐに胃カメラ検査を受けることができない状況であれば、市販の「正露丸」がアニサキスの活動性を抑えて胃の痛みが緩和することがあるという報告もありますので、試してみる価値はあると思います。
腸アニサキス症
腸での発症が疑われる場合には、腹部超音波検査(腹部エコー)などで腸管壁が異常にむくんでいるようなところがないか確認することがあります。ただし、これらの検査ではアニサキスを特定するのが難しい場合が多いため、対症療法が中心です。痛みや不快な症状を緩和しながら、アニサキスが自然に死滅するのを待つことが一般的な治療となります。
消化管外アニサキス症
寄生した部位や症状に応じて治療法が異なります。消化管に穴が開く穿孔や腸閉塞を引き起こす場合があり、外科手術が必要になることもあります。
アニサキスアレルギー
アレルギー反応には抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬、ステロイドを使用します。重症でアナフィラキシーショックを起こした場合には、エピペンや点滴による緊急治療が行います。
発症しないこともある
アニサキスを摂取したからといって必ずしも全員に胃の痛みが発症するわけではなく、全く無症状のまま経過することもあります。そのため、腹痛などの症状が現れないことも少なくありません。こうしたケースでは、別の目的で受けた胃カメラ検査中に偶然発見されることがあります。
放置していても治る?
アニサキスはヒトの体内で長く生きることはできず、体内に入ってから3〜4日で弱り始め、おおよそ1週間で死滅します。しかし、死滅後も症状が続く場合があります。これは、アニサキスが胃や腸の壁に「食いついたことによる痛み」ではなく、アニサキスに対する「アレルギー反応による痛み」が原因となるためです。
そのため、自然に死滅するのを待てば症状が治まるという保証はありません。また、多くのケースでは痛みが非常に強く、数日間我慢するのが難しいことがほとんどです。症状が出た場合は放置せず、医療機関を受診することをお勧めします。
早期対応で安心を
魚介類を食べた後、数日以内に腹痛などの症状を感じた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。内視鏡でアニサキスを取り除くことで症状はすぐに治まります。そのため、症状が出たらできるだけ早く医療機関に連絡し、「アニサキスの可能性がある」と伝えてください。
当院では、アニサキス症の治療に対応した胃カメラ検査を行っています。検査は、内視鏡の専門医が担当し、豊富な実績を基に患者様の苦痛を最小限に抑える配慮をしているため、胃カメラが初めての方でも安心して治療を受けていただけます。アニサキス症の症状が疑われる場合は、ぜひご相談ください。