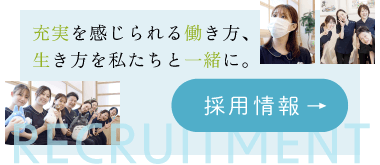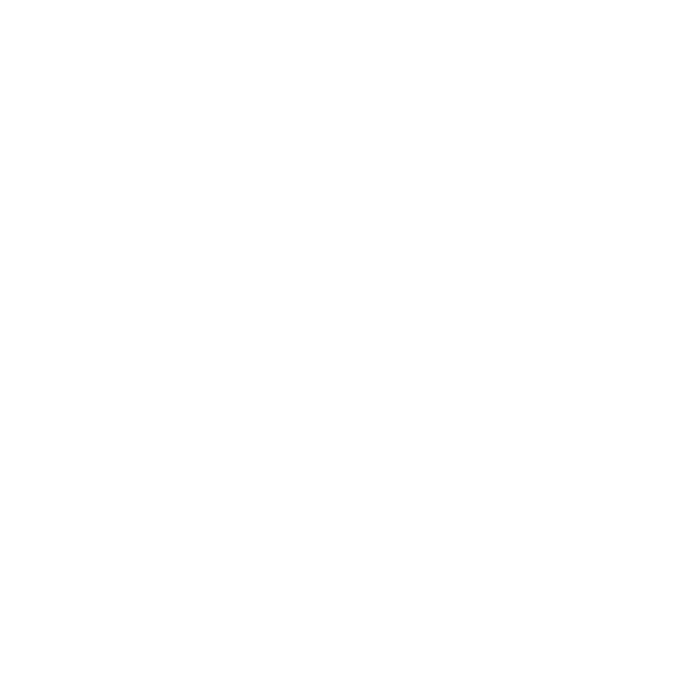便通の変化は、日常生活の中で見過ごされがちですが、体の異常を示すサインかもしれません。「便が出るものの以前よりも細くなった」と感じたり、「便の直径が1cm程度しかない」、「排便後にもスッキリしない」といった状態が続く場合、大腸に何らかの異常がみられる可能性があります。今回は便が細くなる原因について解説します。「最近、便が細くなった気がする…」という方は、ぜひ参考にしてください。

便が細くなる原因は
通常、便の直径は3〜4cmほどが一般的とされていますが、それより細い状態が継続する場合には注意が必要です。原因として考えられるものを紹介します。
腸管の狭窄
なんらかの原因で腸の内側が狭った場合、便が細くなる原因となります。
肛門の狭窄
繰り返し切れ痔が起こると、傷が治る過程で肛門が狭くなり、便が細くなる場合があります。出血が少量であっても、排便時や排便後に痛みがある場合は注意しましょう。
便の性状の変化
便秘の場合、腸内の便から水分が必要以上に吸収されるため、便が硬く細くなることがあります。下痢の場合は、腸の動きが過度に強くなることで、便が十分に形を整える前に排出されてしまうため便が細いと感じることがあります。したがって、便秘でも下痢でも便が細くなることはあり得ることなのです。
加齢による身体の変化
加齢とともに体の筋力が衰えるのと同様に、排便を助ける筋肉も徐々に弱くなり、便が細くなったり、残便感を感じたりしやすくなるとされています。
特に女性は、閉経を迎える時期に体内のエストロゲン(女性ホルモン)の量が急激に減少します。この変化が自律神経のバランスを乱し、腸の働きに影響を与えることがあるのです。このことから、更年期には腸の不調(便通異常)が現れやすいとされています。
食生活や生活習慣
食物繊維や水分の摂取不足、偏食や小食などが便の形状や排便に影響を与える場合があります。また、精神的なストレスは腸の運動に影響を及ぼすため、便の形が不安定になり、便が細くなる原因の1つです。
便が細くなる症状と便秘の関係
便秘とは、便を十分に出せず、排便後もスッキリとしない状態のことです。この状態が続くと、お腹の張りや不快感、さらには吐き気や食欲低下といった症状を引き起こす場合があります。
便が細くなる仕組み
大腸では水分が吸収され、便が固形化されます。便はぜん動運動によって大腸の終わりである直腸に運ばれます。食べ物が体内を通過して便になるまでの時間は通常24〜72時間程度ですが、大腸の動きが鈍くなると腸内に長くとどまりすぎて、水分が過剰に吸収され硬い便となりますが、腸管ぜん動の乱れにより便が細くなる場合もあるとされています。そのため、排便後にも便が残っているような感覚が続く場合があります。
便秘の原因
大きく分けて、機能性便秘と器質性便秘の二種類があります。機能性便秘は腸の動きや排便反射に問題があるもので、生活習慣やストレス、加齢などが主な要因です。
一方で器質性便秘は、腸管自体に構造的な異常(物理的狭窄など)があり、便秘になることです。大腸がんや腸閉塞が原因で腸管が狭くなり便の通過が妨げられ、血便や激しい腹痛を伴う場合もあります。
便が細くなる原因の代表格『大腸がん』
大腸がんは、大腸表面の粘膜から発生する悪性腫瘍のことです。進行すると大腸壁の奥深くまで進展し、腫瘍が大きくなることで、便の通過を妨げたり、出血を引き起こす場合があります。ただし、早期の段階では無症状であることがほとんどです。
便が細くなる仕組み
大腸の中でも肛門に比較的近いS状結腸や直腸に腫瘍ができると、便が細くなる症状が現れやすいとされています。これらの部位は、通常水分が吸収されて固形化した便が通過する部位ですので、大腸がんにより便の通り道が狭くなると便が細くなります(細い便しか通過しない場合もあります)。
症状
便が細くなる他に見られる代表的な症状は、血便、排便習慣の変化(便秘や下痢)、残便感、貧血、腹痛、嘔吐などです。腫瘍の発生部位によって症状が異なりますが、固形化した便が通る結腸や直腸では腸管の狭窄による腹痛や嘔吐、血便が起こりやすくなります。一方、まだまだ水分が吸収されていない泥状の便が通過する盲腸や上行結腸(大腸の奥の方)に発生した大腸がんの場合、通過障害に起因する症状が出にくい代わりに、貧血や腹部のしこりが症状として現れる場合があります。
その他に便が細くなる可能性のある疾患
その他に原因として考えられる病気を紹介します。
大腸ポリープ
初期段階ではほとんど症状が現れませんが、サイズが大きくなり便が通過する腸管内腔が狭くなった場合、便が細くなる場合があります。そのほか、血便や腹部の張り感、下痢などの症状が出る場合もあります。
過敏性腸症候群
腹痛を伴い、下痢や便秘が慢性的に続く疾患で、検査をしても腸に明らかな異常が見つからないのが特徴です。下痢型、便秘型、下痢と便秘を繰り返す混合型、そしてガス型があります。腸管蠕動や腸内細菌のバランスが乱れる影響で便が細くなるだけでなく、残便感や腹部膨満感なども見られることもあります。
炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎など)
腸に炎症が起きることで腸管が狭窄し、便が細くなり、下痢や腹痛、血便といった症状を伴うこともあります。
痔核(いぼ痔)
肛門の血管が腫れることで便の通り道が狭くなるため細い便になり、出血や痛み、かゆみ、粘液を伴う場合もあります。
便が細くなるのを解消する方法は
便が細くなる原因を取り除き、腸の健康を整えることが重要です。生活習慣の改善から始めることで、多くの場合、症状の改善が期待できます。
食生活の改善
食物繊維を多く含む野菜や果物を取り入れることは腸内環境を整えるためにはとても効果的です。
運動習慣
適度な運動は腸の動きを活性化し、便通をスムーズにする助けになります。日常生活にウォーキングや軽いストレッチを取り入れると良いでしょう。
ストレスの解消
ストレスが腸の働きに悪影響を及ぼすこともあるため、リラックスできる時間を意識的に作ることも大切です。
排便習慣の見直し
排便のリズムを整えるためには、便意を感じたときにすぐトイレに行くことが大切です。また、毎日決まった時間にトイレに行き便座に腰掛けることを習慣化することで、腸の働きを保つ助けになります。
医療機関を受診する
生活習慣の改善を試みても症状が続く場合や、血便や腹痛といった異常が見られる場合には、医療機関での検査を受けることが大切です。原因を特定し、適切な治療を受けることが症状の改善につながります。
便が細い場合に行う検査
医療機関では、問診や視診、触診に加えて、必要に応じて以下のような検査を通じて、原因を詳しく調べます。
腹部レントゲン
腹部レントゲン検査は、お腹の内部の状態を確認するための画像診断の一つです。この検査では、腸や胃、膀胱などの消化器や腹部臓器の異常をX線を用いて調べます。腸閉塞や異常なガスのたまり、体内の異物が疑われる場合に有効です。
便潜血検査
便潜血検査は、便の中に目に見えないごく少量の血液が混じっていないか調べる検査です。大腸がんやポリープ、痔などの病気が原因で便に血液が混じる場合がありますが、肉眼では確認できない微量の血液も検出できることが特徴です。この検査は、大腸がんの早期発見や診断のためのスクリーニングとして広く活用されています。
大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)
大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を観察し、大腸ポリープや大腸がんだけでなく腸炎などの早期発見が可能です。また、検査中に発見したポリープを切除することで、大腸がんへの進行を防げます。炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)の診断にも役立ちます。
まとめ
便が細くなったからといって、必ずしも病気が原因とは限りません。しかし、この症状が気になって検査を受けた際に、病気が発見されるケースも少なくないのも事実です。気になる症状があれば、早めに医療機関を訪れ、適切な診断と対処を受けましょう。